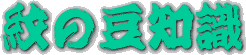
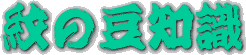
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||||
| 色留袖 | 黒留袖 | 喪服(冬) | 絽喪服(夏) | 色無地 | 小紋 |
| 紋の格について | |
| 染め抜き一つ紋 | 背中に一つだけ付け、色無地や小紋、又色留袖や訪問着等を幅広く着たい時に。 |
| 染め抜き三つ紋 | 背中と両袖に付け、色無地、色留袖等、準礼装としての格を表します。 |
| 染め抜き五つ紋 | 背中に一つと両袖、左右両胸に付ける紋で、黒留袖、色留袖、喪服等、最も格の高い第一礼装です。 |
| 日向紋と蔭紋の違い | ||
日向蔦  |
蔭蔦  |
中蔭ノ蔦 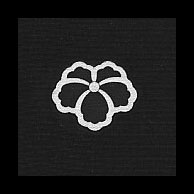 |
| 日向紋が一番格式が高い正装用 の紋に成ります。 |
日向紋より略式です。 紋をあまり目立たせたく無い時にも蔭にします。又、丸無しにした方がより目立たなく成ります。 |
日向紋より略式です。 |
| 丸付き紋と丸無し紋の違い | ||
 |
 |
|
| 丸に五三ノ桐 | 丸無しの五三ノ桐 | |
| 紋の標準位置 | |
| 前紋(左右両胸) | 後ろ両袖と背紋 |
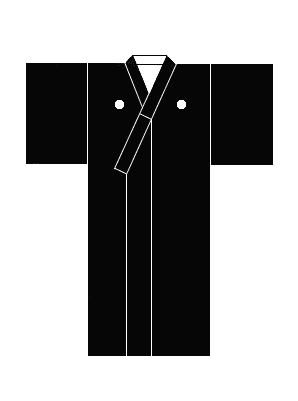 |
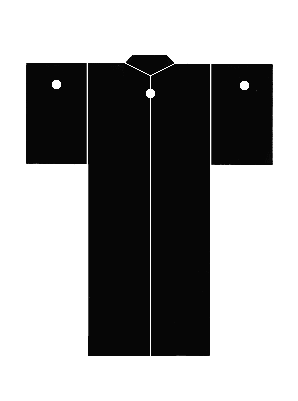 |
| 前紋 肩山から4寸(15.2cm)及び4寸5分(17cm) |
袖紋 : 肩山から2寸(7.5cm) 背紋 : 襟付けから1寸5分(5.7cm) |
| 紋入れの種類 | |||
| 加賀紋 |
自分の家の定紋(家紋)以外に、好みの花や日常品を、図案化したものや 紋の周りに花などをあしらい、それらを彩色したもので、遊び着や振袖に利用されます。 (別名:染め加賀とも言います。)画像 |
||
| 抜き紋 | 紋の形に合わせた抜き型で、紋を入れる所を白く抜き、そこへ紋を描き入れます。 (別名:紋抜き・染め抜き紋・染め抜き入れ紋とも言います。)画像 |
||
| 摺り込み紋 | 摺り込み型で、染料や顔料(漆、カシュー漆)等を刷毛で摺り込んでゆく 好みの色や、ぼかし風にしたりと、いろいろ楽しめます。(別名:摺り紋とも言います。)画像 |
||
| 石持ち入れ紋 | 石持ち入れ紋とは、紋を入れるところが、丸く染まっておらず、白くなっています。 それを(石持ち)と呼びますが、その丸の中に紋を描き入れることを言います。 (別名:描き紋・石持ち紋とも言います。)画像 |
||
| 切りつけ紋 | 切り付け紋は、紋を替えたいとき、染めが抜けずに紋抜きが出来ないとき 又、生地が弱っていて抜き替えが難しいときなどに用います。 色でも黒でも、模様の中でも付けられるので大変便利です。 (別名:貼り紋とも言います。)画像 |
||
| のり落とし上絵 | 白生地のうちに、紋を付ける場所へ表と裏にゴムのりを伏せ (紋を入れる所が染まらないように) 染めたのちゴムのりを落とし、そこへ描き入れます。画像 |
||
| 素描紋 | 紋の中に地色が無く、輪郭も中のしべも、すべて線だけで描かれた紋を言います。 (別名:線描き紋とも言います。)画像 |
||
| 紋章上絵師とは・・・? |
| 紋章上絵師とは日本古来の伝統的技法により、手描きで着物に家紋を入れる人のことです。 又、紋章上絵師、上絵師、上絵屋さん、紋屋さん、とも呼ばれています。 上絵とは、紋を手で描き入れることを意味します。つまり手描きでない紋は上絵とは言いません。 |
| 「紋武」って・・・? |
「紋武」は、「もんたけ」と読みます。 家紋の(紋)と名前の一字から(武)をくっ付けたものです。 これは昔からの紋章上絵師、個人に対する呼び方の一つで、 お店でいうと「屋号」、絵師で言うなら「雅号」のようなもの・・・ 上絵師にとっては屋号と雅号の両方の意味合いがあるのです。 私の先代である父の師匠は「紋金・もんきん」と言いました。 名前が金五郎だったからです。昔ならではの名前ですね・・・ 父の名は「清・きよし」だったので「紋清・もんきよ」 私は「武雄・たけお」なので「紋武・もんたけ」となるんです。 今はほとんど、こう言う呼び方はしなくなってしまったのですが、 たまに、古くからのお客さんから、紋武さん、なんて呼ばれると、 何だか嬉しくなっちゃうのです・・・・。 |
![]()
伝統手描き紋章上絵
伊藤紋章店 「紋武」
Copyright©「無断複写・複製・転載を禁ず」
Sorry,This Page is Japanese Only